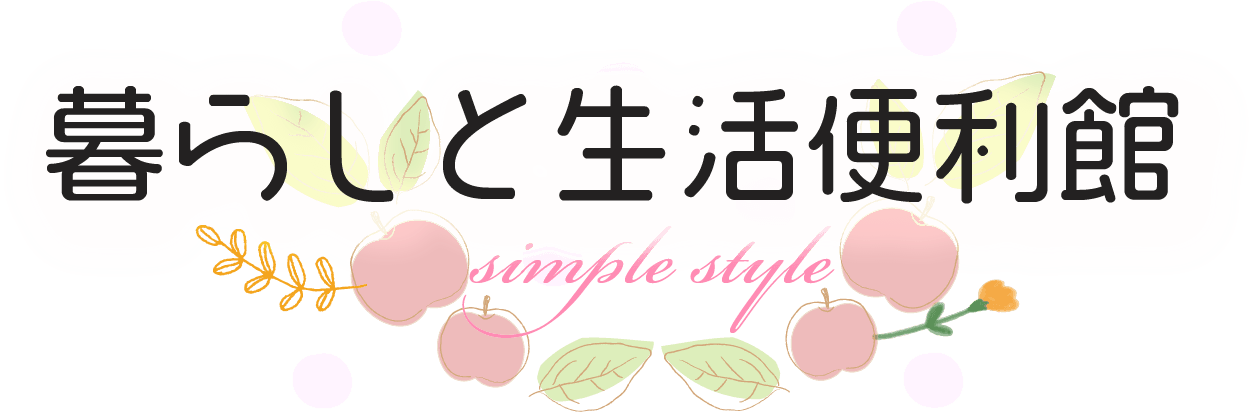家が売れない ストレスから抜け出すために|空き家所有者が知るべき準備と相談のタイミング
相続した実家がなかなか売れず、経済的負担や管理の手間にお悩みではありませんか?実は、全国の空き家数は900万戸を超え、その多くが相続によるものです。家が売れない背景には、立地や建物の状態、権利関係など様々な要因があります。この記事では、空き家問題の現状と売れない家の特徴、そして所有者が感じるストレスを軽減するための具体的な対策について、詳しく解説します。
- 家が売れないストレス!その背景にある空き家問題の深刻化
- なぜ今、空き家がこれほど増えているの?
- 相続した家が売れないのはなぜ?チェックしたい5つの特徴
- 相続した家が売れないとどうなる?
- 空き家所有で感じる経済的負担とストレス
- 解体するにもお金がかかる現実
- 遠方にある実家の管理ってどうするの?
- 家が売れない ストレスを軽減するための対策
- 高齢者が今からできる準備とは
- 専門家に相談すべきタイミングはいつ?

家が売れないストレス!その背景にある空き家問題の深刻化
なぜ今、空き家がこれほど増えているの?
日本の空き家問題が深刻化している背景には、高齢化社会と少子化という構造的な問題があります。消費経済アナリストによると、親世代の高齢化により、実家で一人暮らしをしていた高齢者が入院や介護施設に入ることで空き家が生まれるケースが増えているとされます。
総務省が公表した最新データでは、全国の空き家数は約900万戸に達し、これは約30年前の2倍にあたる数字です。住宅総数に占める割合は13.8%で、実に7軒に1軒が空き家という状況になっています。
注目すべきは、賃貸用や別荘を除いた「使用目的のない空き家」が約386万戸もあることでしょう。これは全体の5.9%を占め、5年前と比較して37万戸近く増加している現実があります。
地方だけの問題と思われがちですが、実は都市部でも空き家は増加傾向にあると考えられています。人口が集中している都市部においても、この問題は無関係ではないといえるでしょう。
少子化による人口減少と都市部への人口集中も、空き家増加の要因として挙げられています。地方から都市部に移住した子世代が、親の住んでいた地方の実家を相続するパターンが典型例かもしれません。
相続した家が売れないのはなぜ?チェックしたい5つの特徴
親から相続した大切な家。しかし、いざ売却しようとしても、なかなか買い手が見つからずに悩んでいませんか?「何か問題があるのだろうか...」と不安に感じている方も多いかもしれません。
実は、売れにくい家には共通する特徴がいくつかあります。この記事では、なぜご自身の家が売れないのか、その原因となる5つの特徴を分かりやすく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、解決の糸口を見つけていきましょう。
特徴1:立地が良くない
不動産の価値を大きく左右するのが「立地」です。買い手は、これからの生活の利便性を非常に重視します。
- 交通の便が悪い: 最寄り駅から遠い、バスの本数が少ないなど、都心部へのアクセスが不便な場所は敬遠されがちです。
- 周辺環境の問題: 「近くにスーパーや病院がない」「学校が遠い」「坂道が多い」といった生活のしにくさもマイナスポイントになります。
- 過疎化が進むエリア: 人口が減少している地域では、将来的な資産価値に不安を感じる買い手が多く、需要そのものが少なくなります。
ご自身の家の周りの環境を、買い手の視点でもう一度客観的に見直してみましょう。
特徴2:家の状態が悪い(老朽化)
家の「状態」も、買い手の購入意欲に直結する重要な要素です。特に相続した家は、築年数が経過しているケースが多く見られます。
- 築年数が古い: 旧耐震基準(1981年5月以前)で建てられた家は、耐震性に不安を感じる買い手が多く、住宅ローン控除などの税制優遇が受けられない場合もあるため、売却が難しくなる傾向があります。
- 建物の劣化や不具合: 雨漏り、シロアリの被害、壁のひび割れ、設備の故障(給湯器、エアコンなど)といった目に見える問題があると、修繕費用がかさむため買い手は購入をためらいます。
- 見た目の印象: 外壁の汚れや庭の荒れなど、ぱっと見の印象が悪いと、内覧にすら進んでもらえない可能性があります。
「住めれば良い」ではなく、「住みたい」と思ってもらえる状態かどうかが鍵となります。
特徴3:権利関係が複雑
見た目や立地だけでなく、法律上の問題が売却の障壁になることもあります。
- 共有名義になっている: 兄弟姉妹など、複数の相続人で家を共有している場合、売却には共有者全員の同意が必要です。一人でも反対すると売却はできません。
- 土地の境界が未確定: 隣地との境界がはっきりしていないと、後々のトラブルを恐れて買い手は購入を避けます。
- 再建築不可物件: 建築基準法上の道路に接していないなどの理由で、今ある家を取り壊すと新しい家を建てられない土地は、活用方法が限られるため売却が非常に困難です。
こうした権利関係の問題は、専門的な知識が必要になるため、気づかないうちに売却の足かせになっているケースも少なくありません。
特徴4:価格設定が相場と合っていない
「できるだけ高く売りたい」という気持ちは誰にでもありますが、周辺の相場からかけ離れた価格設定では、買い手は興味を示してくれません。
- 高すぎる価格設定: 周辺の類似物件の売出価格や成約価格をリサーチせず、一方的に高い価格をつけているケースです。
- 「思い出」価格になっている: 「親が大切にしていた家だから」という気持ちが先行し、客観的な価値判断ができていない場合も注意が必要です。
売却活動が長期化するほど、家の管理費用がかさみ、市場での印象も悪くなってしまいます。適正な価格設定が、売却成功への第一歩です。
特徴5:管理状態が悪い
相続後、空き家になっている家は管理が行き届かなくなりがちです。管理状態の悪さは、家の価値を大きく下げてしまいます。
- 庭や外観の荒れ: 雑草が生い茂り、郵便物が溜まっていると、管理されていない印象を与え、防犯上の不安も感じさせます。
- 室内に残置物が多い: 荷物が散乱していると、部屋の広さや状態が分かりにくく、買い手は自分の生活をイメージできません。また、購入後の片付けの手間を考えて敬遠してしまいます。
- カビや悪臭: 長期間換気されていない家は、カビやホコリっぽさで不衛生な印象を与えてしまいます。
定期的な清掃や換気、庭の手入れなど、基本的な管理を続けることが大切です。
相続した家が売れないとどうなる?
相続した家がなかなか売れず、「そのうち買い手が見つかるだろう」と、つい問題を先延ばしにしていませんか?
実は、売れない家をそのまま放置してしまうと、金銭的な負担が増えるだけでなく、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。この記事では、家が売れない状態が続くと具体的にどのようなことが起こるのか、知っておくべき5つのリスクを解説します。
1. 終わりなき経済的負担
最も現実的なリスクは、所有しているだけでお金がかかり続けるという点です。たとえ誰も住んでいなくても、毎年課される固定資産税や都市計画税の支払い義務がなくなることはありません。それに加え、火災保険料や最低限の水道光熱費、庭の手入れを業者に依頼する費用など、建物を維持するための管理費も継続的に発生します。
さらに、ある日突然雨漏りが見つかるなど、予期せぬ高額な修繕費が必要になることもあり、ケースによっては年間で数十万円の出費に達することもあります。売却が長引くほど、この経済的な負担がご自身の家計を圧迫し続けます。
2. 時間と共に失われる資産価値
「時間が経てば、もっと高く売れるかも」という期待は、残念ながら空き家には当てはまりません。むしろ、時間は資産価値を奪っていきます。人が住まない家は換気が滞って湿気がこもりやすいため、驚くほど速く劣化が進みます。
カビやシロアリが発生し、家の土台である柱や壁が腐食していくのです。その結果、いざ売却しようと思った時には建物の老朽化が進みすぎて、「土地の値段でしか売れない」「解体費用を値引きしないと買い手がつかない」といった厳しい状況に陥りがちです。売り時を逃せば逃すほど、大切な資産が目減りしていくという悪循環に陥ってしまいます。
3. ご近所トラブルという新たな火種
管理されていない空き家は、ご近所の方々にとっても不安の種となり、思わぬトラブルの原因になります。例えば、庭の雑草が生い茂って隣の敷地にはみ出したり、ネズミや害虫の住処となって周囲に被害を及ぼしたりすることがあります。
さらに深刻なのは、老朽化したブロック塀や屋根材が、台風や地震で倒壊・飛散し、隣家や通行人に怪我をさせてしまうケースです。万が一、所有する空き家が原因で他人に損害を与えてしまった場合、所有者として損害賠償責任を問われる可能性も十分にあります。
4. 犯罪を呼び寄せる危険性
人の出入りがない空き家は、残念ながら犯罪のターゲットにされやすいという現実があります。夜間は特に目立ちにくいため、窓ガラスを割られて不法侵入されたり、最悪の場合は放火されたりする事件が報じられることもあります。
また、犯罪グループの隠れ家や違法な物品の保管場所として利用されるなど、地域の治安を悪化させる原因にもなりかねません。
5. 税金が最大6倍になる「特定空家」のリスク
放置された空き家が社会問題となる中、「空家等対策特別措置法」という法律が施行されました。この法律に基づき、倒壊の危険性が高い、あるいは衛生上有害であると行政が判断した家は「特定空家」に指定されることがあります。
指定されると、まず行政から改善の助言や指導が行われますが、それでも従わない場合は「勧告」へと進みます。この勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、固定資産税額が最大で6倍相当まで増える場合があります。
さらに放置を続けると、最終的には行政によって家が強制的に解体され、その高額な費用が所有者に請求されることになります。これは空き家を所有する上で最大級のリスクと言えるでしょう。

空き家所有で感じる経済的負担とストレス
解体するにもお金がかかる現実
空き家が売れないからといって、簡単に解体すれば良いというものではありません。専門家が指摘するように、空き家を壊すのにも相当な費用がかかるのが現実です。
一般的な住宅の解体費用は、建物の構造や立地条件によって変動しますが、木造住宅の場合1坪あたり3万円〜6万円が目安となり、標準的な30〜35坪では90万円〜200万円程度が相場です。また、重機の搬入が難しい、アスベストの有無、残置物の量によっては解体費用が更に高額となる傾向があります。
解体後の土地についても、必ずしも売却できるとは限らないのが実情かもしれません。立地条件が悪い土地や需要の少ない地域では、解体費用をかけても結果的に売れ残ってしまうリスクがあるといえます。
このような状況から、空き家の所有者は「売ることも壊すこともできない」というジレンマに陥り、大きなストレスを抱えることになるかもしれません。
遠方にある実家の管理ってどうするの?
空き家を遠方に持つ所有者が直面する最も大きな課題は、定期的な管理の難しさでしょう。建物は人が住まなくなると急速に劣化が進むため、定期的な換気や清掃、設備の点検が必要になります。
しかし、車や電車で1時間以上かかる場所にある実家を頻繁に訪れるのは、時間的にも経済的にも負担が大きいといえるでしょう。交通費や時間を考慮すると、定期的な訪問や管理が難しくなるケースも少なくありません。
管理が行き届かない空き家は、雨漏りやカビの発生、害虫の侵入などの問題が起こりやすくなります。これらの問題が深刻化すると、建物の価値がさらに下がり、売却がより困難になる悪循環に陥る可能性があるでしょう。
また、空き家の中に家具や家電、思い出の品々が残されている場合、その処分も大きな負担となります。遠方からでは処分業者との打ち合わせや立ち会いも困難で、何度も往復する必要が生じるかもしれません。
固定資産税の支払いも続く一方で、空き家からの収入は全くないため、所有者にとっては純粋な負担となってしまうのが現実といえます。

家が売れない ストレスを軽減するための対策
高齢者が今からできる準備とは
専門家は、自宅が空き家になりそうな高齢者は「考える時期にきている」と指摘しています。将来的に家が負債になることを避けるためには、早めの準備が重要でしょう。
まず取り組むべきは、家の中の荷物や家財の整理です。生前整理の標準的な流れとしては、不要品や長年使っていないものを選別し、家族や知人と分けたり処分を進めていくことが推奨されています。
生前整理を進めることで、相続時に家族が感じる負担を大幅に軽減できるでしょう。家財を整理するだけでなく、財産の目録を作成し相続財産をリスト化しておくことも役立ちます。
また、子どもたちが家を出て高齢者が広い家に一人で住むようになった段階で、将来の住まいについて具体的に検討することも重要といえます。ワンルームマンションへの住み替えや、介護付き老人ホームへの入居など、複数の選択肢を検討しておくべきでしょう。
専門家は「ポジティブなライフプランを組むこと」の重要性も強調しており、空き家問題を単なる負担として捉えるのではなく、より良い未来につなげるための機会として考えることが大切かもしれません。
専門家に相談すべきタイミングはいつ?
空き家問題には遺産相続や固定資産税など、複雑な法的・税務的な要素が絡んでくるため、専門家への相談が不可欠でしょう。アナリストも「専門家に相談した方がいい」と明確に述べています。
相談すべきタイミングとしては、親が元気なうちに家族全体で将来について話し合うことが理想的かもしれません。親の意向を確認しながら、相続や売却について事前に検討しておくことで、いざという時の混乱を避けることができるでしょう。
不動産の専門家や税理士、弁護士などに相談することで、その家の市場価値や売却の可能性、税務上の注意点などを事前に把握できます。早期に専門的なアドバイスを受けることで、最適な対策を立てることが可能になるかもしれません。
また、国の法整備も進んでいますが、「それを待っているだけでは改善されない」と専門家は指摘しています。行政の対応を待つのではなく、個人レベルでできる対策を積極的に講じることが重要といえるでしょう。
空き家問題は日本の個人消費にも大きく影響する社会問題として捉えられており、早めの対応が個人にとっても社会にとっても有益な結果をもたらすと考えられています。