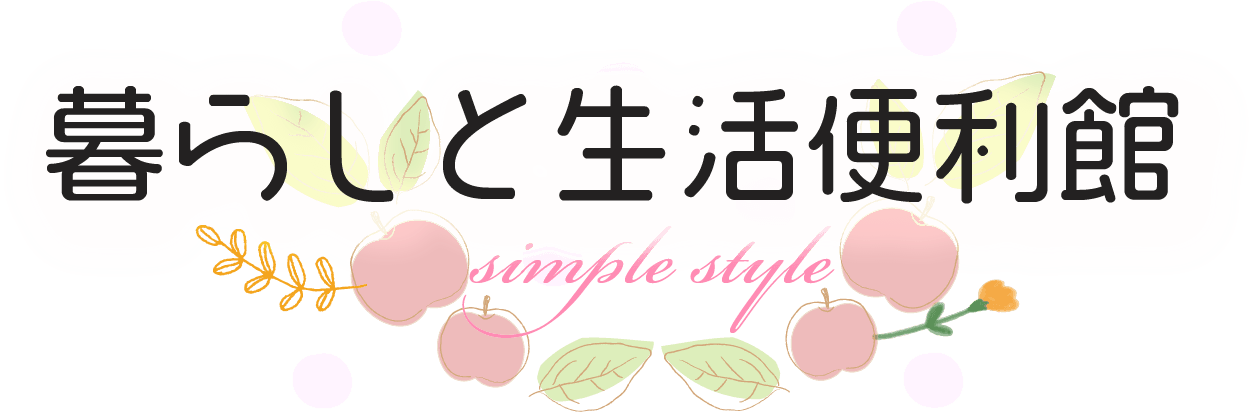論理的思考が苦手でも大丈夫|できない原因を知って自分らしい伝え方を見つけよう
話をするとき、頭の中に言いたいことはあるのに順序立てて説明できない。論理的思考ができないと感じて、自分を責めてしまうことはありませんか? 実は、論理的に考えられないのは決してあなただけではありません。思考の得意・不得意には個人差があり、感覚的に物事を捉える人も、直感を重視する人もいます。 この記事では、論理的思考が苦手になる原因から、自分の思考パターンを整理する方法、さらには論理が苦手でも相手に伝わる説明のコツまで、具体的にお伝えします。「できない」と感じる自分を責める前に、まずは自分なりの考え方や伝え方を見つけてみませんか?
- 論理的に思考できないのは、誰にでもあること
- まず「できない」と感じる自分を否定しない
- 「論理的でなければダメ」という思い込み
- 論理的思考が苦手になる原因とは?
- 性格的な傾向(感覚優位型・直感型)
- 育ってきた環境や教育の影響
- 実は「情報過多」で頭が混乱しているだけかもしれない
- 自分の思考パターンを整理する
- 「感情と思考」が混ざっていないかチェックする
- 「結論→理由→具体例」で考えてみる練習
- 頭の中の「もやもや」を見える化する方法
- 論理的思考が苦手でもできること
- 「論理」が苦手でも伝わる説明の工夫
- 共感力や直感力は、別の強みになる
- 「伝えること」より「伝わること」に意識を向ける
- 論理的に思考するための2つの武器 ― ロジックツリーとMECE
- ロジックツリー ― 問題を「ほぐす力」を鍛える思考法
- MECE ― 情報の「抜け」と「かぶり」を見逃さないために
- もし思考がどうしてもまとまらないなら
- ADHD・HSPなどとの関係は?
- 疲れ・ストレス・不安が思考力を下げることも
- 「論理思考」以外の自分の価値に気づく

論理的に思考できないのは、誰にでもあること
まず「できない」と感じる自分を否定しない
話をしているとき、頭の中に言いたいことはあるのに、順序立てて説明できない。その瞬間、なんだか自分が人より劣っているように感じてしまうかもしれません。でも、それはあなただけではありません。どんなにしっかりして見える人でも、ふとした拍子に「うまく伝えられない」と感じてしまう場面があります。
論理的に話せない、思考がまとまらない。それだけで「自分は頭が悪いのかもしれない」「なんでこんな簡単なこともできないんだろう」と自分を責めてしまいそうになる。でもその感覚は、むしろ「真剣に考えている証拠」でもあるのです。
大切なのは、「できない」と感じた瞬間に、自分を否定しすぎないこと。誰でも、思考の得意・不得意はあります。少し混乱してしまうときがあっても、それでその人の価値が下がるわけではありません。
「論理的でなければダメ」という思い込み
「論理的でなければ評価されない」「ロジカルじゃないと仕事ができない人と思われる」──そんな言葉をどこかで聞いたことがあるかもしれません。でも本当にそうでしょうか?
社会の中では、確かに論理的思考が求められる場面が多くあります。でも、「論理=正義、感情=間違い」と決めつけてしまうと、かえって自分の考え方に自信を持てなくなってしまいます。
論理的であることはひとつの「思考の型」にすぎません。感覚や直感、経験に基づいて考えることも立派な思考です。大事なのは「自分の考えをどうやって整理し、人に伝えるか」。論理はその手段のひとつであって、唯一の正解ではありません。
論理的思考が苦手になる原因とは?
性格的な傾向(感覚優位型・直感型)
論理的思考が得意な人とそうでない人。その違いは、必ずしも「知識量」や「頭の良さ」ではありません。むしろ、生まれ持った思考の傾向や、どんな情報に強く反応するかといった"感じ方"の違いが大きく関係しています。
例えば、何かを考えるときに「感覚的にこうだと思う」とか「なんとなくこう感じた」と直感的に結論にたどりつくタイプの人もいます。そういう人にとって、順序立てて理由を説明するのは、少し窮屈で疲れる作業かもしれません。
これは欠点ではなく、思考のスタイルのひとつです。音楽やアート、人との会話の雰囲気に敏感だったり、場の空気を自然に読める人には、感覚や直感を大切にする傾向があります。
その一方で、順序だてて理屈で説明するのが得意な人もいます。いわゆる「論理的なタイプ」です。ただし、どちらが優れているという話ではなく、大切なのは「自分がどちらの傾向に近いかを知る」ことです。
育ってきた環境や教育の影響
「論理的に考える力」は、先天的なものというより、後天的に"訓練されてきたかどうか"の影響がとても大きいと一般的に言われています。
子どもの頃から「なぜそう思ったの?」と親や先生に問われてきた人は、自分の考えを筋道立てて話す力が自然と身についています。一方で、「とにかく結果だけ言いなさい」「空気を読みなさい」といった文化の中で育つと、思考のプロセスを言語化する練習をする機会が少なくなります。
学校の授業でも、「答えを早く出す」ことが重視された環境では、過程を言語化する力が育ちにくいことがあります。そうした背景があると、大人になってから「論理的に話せない」と悩むのも当然のことです。
つまり、論理的思考が苦手と感じているのは、あなたが劣っているからではなく、「訓練する機会が少なかっただけ」なのかもしれません。
実は「情報過多」で頭が混乱しているだけかもしれない
今の時代、私たちは日々膨大な情報にさらされています。スマホを開けばニュース、SNS、広告、通知が飛び込み、脳は常に処理に追われている状態です。
そんな環境では、「何をどう整理して考えればいいのか」がわからなくなるのも無理はありません。頭の中に情報が詰まりすぎて、まるで混線したコードのようになっていることもあるのです。
この状態では、考えようとしても「もやもや」してしまい、思考の筋道が見えなくなってしまいます。決して能力が足りないわけではなく、整理されていないだけ。まずは「何が頭に詰まっているのか」を外に出してみることが、突破口になるかもしれません。
自分の思考パターンを整理する
「感情と思考」が混ざっていないかチェックする
何かを伝えようとしたとき、「うまく言えない」「頭の中がごちゃごちゃしている」と感じたことはありませんか?その理由のひとつに、「感情」と「思考」が絡まり合っている状態が挙げられます。
たとえば、「上司の言い方が冷たかった」と感じたとき、その感情の裏にある「なぜそう思ったのか」という分析がないままだと、心の中でモヤモヤが大きくなっていきます。そして、そのモヤモヤを説明しようとすると、どうしても話が感情寄りになり、論理的に聞こえにくくなってしまいます。
このように、感情が先に立ちすぎてしまうと、思考の筋道があいまいになります。だからといって感情を否定する必要はありません。ただ、「私は今、何に怒っているのか?」「どんな出来事がきっかけだったか?」と、一歩引いて整理してみることで、少しずつ思考と感情を分けて捉えられるようになります。
それが「考えを言語化する力」を育てる第一歩になるのです。
「結論→理由→具体例」で考えてみる練習
論理的に話すとは、要するに「相手が理解しやすい順序で話すこと」です。そのための基本的な順番が「結論→理由→具体例」の流れです。
こんな場面を想像してみてください。
✕「この前A社に訪問して...担当者が不在だったんですが、メールでやりとりして...それで来週また会う予定です」
◎「来週、A社の担当者と面談の予定が入りました(結論)。前回訪問時は不在でしたが、メールで調整を進めました(理由)。メール内容は、導入製品の候補についての相談です(具体例)」
順番が変わるだけで、受け取る側の理解がぐっと深まります。 慣れないうちは、口に出す前に紙に書いてみるのも効果的です。 いきなり論理的に話そうとするのではなく、「型をまねる」くらいの気軽さで始めると、少しずつ自然にできるようになっていきます。
頭の中の「もやもや」を見える化する方法
考えがまとまらないとき、その多くは「頭の中で情報が循環し続けている状態」です。思いついたことが次々浮かんで、どこから話せばいいか分からなくなってしまう。
そんなときは、無理に頭の中で整理しようとせず、「書いて外に出す」ことを試してみてください。
- 白紙に思いつくことを箇条書きで書き出す
- 「原因」と「結果」に分けてメモをとる
- 人に話すつもりで、ノートに説明文を書いてみる
これだけでも、ぐるぐる回っていた思考が静かになり、自分が何を考えていたのかが見えやすくなります。
思考の整理は「頭の中でやるもの」と思いがちですが、紙やスマホメモを使って外に出すだけで、視点がぐっと変わってきます。言葉にしようとした瞬間に、脳が情報を整頓しはじめるのです。

論理的思考が苦手でもできること
「論理」が苦手でも伝わる説明の工夫
論理的に話せないと「説明が下手だ」と思われるのでは、と不安になることがあります。でも、実際には、論理よりも「伝わりやすさ」を重視することで、会話はずっとスムーズになることも多いのです。
専門的な用語を多用せずに話す。相手の関心に合わせて話す内容を選ぶ。例え話を使って説明する。これらはすべて、「伝わる説明」のための工夫です。
論理的な構成を完璧にすることよりも、「相手に届く言葉を選ぶこと」に意識を向けると、思いがけず相手とのコミュニケーションが良くなることもあります。話し方の正解はひとつではありません。論理が苦手でも、あなたなりの伝え方で心を動かせることがあります。
共感力や直感力は、別の強みになる
論理的に話せる人が目立ちやすい世の中ではありますが、それが全てではありません。人の表情に敏感だったり、話の行間を自然に感じ取ったり、そういった「察する力」「共感力」も立派な能力です。
会議中に場の空気が悪くなっているのをいち早く察して声をかけられる人。クライアントの表情から言葉にしない要望をくみ取れる人。こうした力は、論理だけでは補えないものです。
自分では「なんとなく」で判断していると思っていても、それは経験や感覚から得た確かな直感なのかもしれません。
論理的であることが苦手だと感じたときこそ、自分の別の力に気づくチャンスでもあります。目に見えにくいけれど、確かに人の役に立っている能力はたくさんあるはずです。
「伝えること」より「伝わること」に意識を向ける
説明するとき、「正確に話そう」と意識しすぎるあまり、言葉が詰まってしまうことはありませんか?論理的に整っていなくても、相手に伝わっていれば、それで十分な場面はたくさんあります。むしろ、「何を伝えるか」よりも、「相手がどう受け取ったか」に重きを置いたほうが、結果として良いコミュニケーションになることもあります。
話の途中で「うまく言えないんだけど...」と正直に打ち明ける。それだけで、相手の気持ちは柔らかくなります。あるいは、図やメモを使って話すと、言葉の足りなさを補ってくれます。言葉だけで完璧に伝えようとせず、あなたなりの「伝わる工夫」を見つけてみる。そんな姿勢が、相手との距離をぐっと縮めてくれるかもしれません。
論理的に思考するための2つの武器 ― ロジックツリーとMECE
ロジックツリー ― 問題を「ほぐす力」を鍛える思考法
何かがうまくいっていないとき、「とりあえず解決しよう」と焦ってしまうことはよくあります。でも、その前に必要なのは、「いま自分が直面している問題が、どんな構造になっているのか」を見きわめることです。
そのための道具が、ロジックツリー。テーマや課題を「なぜ?」「どうやって?」と繰り返しながら、枝を分けていくことで、複雑な問題の"地図"を描くように整理する方法です。
たとえば、「売上が下がっている」という問題を目の前にしたとします。そのままだと漠然としすぎて、どこから手をつけるべきかが見えません。でも、ここで「なぜ売上が下がっているのか?」と問いかけてみる。
「購入者が減った」という答えが浮かんだとしましょう。さらに「なぜ購入者が減ったのか?」と考えると、「ホームページのアクセスが落ちている」という原因にたどり着くかもしれません。そこから「なぜアクセスが落ちたのか?」と掘り下げていくと、「SNSでの発信が止まっていた」といった、非常に具体的な原因が見えてきます。
■なぜ売上が下がっているのか?
- なぜ? → 購入者数が減った
- なぜ? → ホームページのアクセス数が落ちている
- なぜ? → SNSでの発信が止まっていた
これはつまり、「問題だと思っていたものは、もっと小さな要因の積み重ねだった」という構造に気づく作業です。ツリーの枝をたどっていけば、自然と「今やるべきこと」が浮かび上がります。
逆に「どうすれば改善できるか?」という発想から始めて枝を広げていく使い方もあります。「お問い合わせを増やしたい」という目標に対して、「ホームページを改善する」「広告を出す」「FAQを充実させる」といった手段をいくつか挙げ、それぞれをさらに分解していく。
■お問い合わせを増やしたい:
- どうやって? → ホームページを改善する
→ 問い合わせボタンを目立たせる → よくある質問を追加する - どうやって? → 広告を使う
→ SNS広告 → リスティング広告
このように、ロジックツリーは「問題の奥を掘り下げる」こともできれば、「手段の幅を広げる」ことにも使える万能ツールです。ただし、いきなり正しいツリーを描こうとする必要はありません。最初は紙に思いつくことをどんどん書き出して、あとから整理する形でも十分です。
ロジカルに考えるとは、「思いつき」を捨てることではなく、「思いつきを構造に変える」作業。ツリーは、そのための支柱になってくれます。
MECE ― 情報の「抜け」と「かぶり」を見逃さないために
問題を整理しているつもりなのに、どうも頭がごちゃつく。そんなとき、実は「情報の分け方」が歪んでいるケースがよくあります。
MECE(ミーシー)は、「モレなく、ダブりなく」情報を整理するための原則です。情報の整理が苦手な人の多くは、この"モレ"や"ダブり"に気づいていません。そして気づかないまま話し始めて、「何が言いたいのか分からない」と言われてしまいます。
転職活動を整理するとき、「自己分析」「履歴書」「面接対策」の3つに分けたとしましょう。一見、整理されているように見えますが、この分け方には"モレ"があります。「企業調査」や「進捗管理」が含まれていない。そして「履歴書」と「職務経歴書」がごっちゃになっていて、情報の"ダブり"も起きています。
MECEで考えるときは、まず「どういう軸で分けるのか?」を意識するのがポイントです。
「準備の手順」という軸を選ぶと、
- 自己分析
- 情報収集
- 書類作成
- 応募管理
- 面接対策
日常の中でも、MECEは有効です。たとえば休日の予定を立てるとき、「やりたいことリスト」が頭の中にあると混乱しやすいですが、MECEの考え方で
- 体を休めること
- 心を満たすこと
- 生活を整えること
注意点は、完璧を目指しすぎないこと。MECEは"後から整える"こともできます。まずは手元の情報をいったん分類してみて、重複している部分や漏れている部分を探す。そうやって修正していく過程で、思考がどんどんクリアになっていきます。
論理的に話すには、「自分が何をどう分けて考えているか」を意識できるかどうかがカギになります。MECEはその"整理の筋肉"を育ててくれる、非常に実用的な思考法です。
もし思考がどうしてもまとまらないなら
ADHD・HSPなどとの関係は?
「何を考えようとしても、頭が整理できない」「話している途中で別のことを思い出してしまう」──こうした状態が頻繁にあると、自分の思考そのものに不安を感じることがあります。
中には、ADHD(注意欠如・多動症)やHSP(非常に敏感な気質)といった、認知や感受性の特徴が関係している場合もあります。これらは病気ではなく、その人の思考や感覚の"傾向"です。
ADHDの傾向がある人は、複数の情報が同時に頭に浮かんで整理しにくかったり、話しているうちに話題が飛んでしまうことがあります。HSPの人は、相手の反応や感情に過敏に反応しすぎて、自分の考えをまとめづらくなることがあります。
もし、日常生活や仕事に支障が出るほどの困りごとがあるなら、医療機関やカウンセリングなど専門的なサポートを頼るのもひとつの方法です。
大切なのは、「論理的に考えられないのは自分が怠けているからだ」と思い込まないこと。生まれつきの特性や脳の働き方には個人差があるという視点を持つことで、自分の思考との向き合い方が少し楽になるかもしれません。
疲れ・ストレス・不安が思考力を下げることも
論理的に考えられないとき、意外と見落とされやすいのが「脳の疲れ」です。睡眠不足、過度なストレス、不安、緊張状態──これらが続くと、脳は"情報を処理する力"を下げてしまいます。たとえるなら、パソコンが熱暴走して動作が鈍くなっているような状態です。
とくに真面目でがんばりすぎる人ほど、頭がうまく回らない自分を責めてしまいがちです。でも実は、頭が働いていないのではなく、「休むべきときに休めていないだけ」かもしれません。集中できないときは、深呼吸をしたり、散歩に出てみたり、意識的に脳を「オフ」にしてみましょう。考える力は、休んだぶんだけ回復します。
「論理思考」以外の自分の価値に気づく
論理的に考えることが苦手だと、「自分には価値がないのでは」と感じてしまうことがあります。でも、本当にそうでしょうか?「言葉にしづらいけれど、なんとなく相手の気持ちがわかる」 「複雑な状況でも、人の気持ちに共感できる」 「誰かの話を、最後まで丁寧に聞いてあげられる」
こうした力は、論理とは別の"人間らしい知性"です。論理的思考が得意な人もいれば、情緒的な理解や直感で動ける人もいます。どちらが上で、どちらが下ということではありません。
「自分にできること」を見つめ直すこと。それは、論理的になるための訓練よりも、もっと大切なことかもしれません。
よくある質問(FAQ)
論理的に考えられないのは性格の問題ですか?
性格だけでは判断できません。思考の傾向には個人差があり、感覚的に物事を捉える人もいれば、直感型の人もいます。また、論理的思考の訓練を受けてこなかった環境要因も影響します。性格を理由に決めつけず、自分のスタイルに気づくことが第一歩です。
論理的思考が苦手でも仕事に支障はありませんか?
必ずしも支障があるわけではありません。論理的思考は一つのスキルであり、すべての職場や業務で必須というわけではありません。共感力や気配りといった他のスキルで補えることも多く、自分に合ったやり方を見つけていくことが大切です。
どうしても話が長くなってしまいます。どうすれば良いですか?
話が長くなるのは、伝えたいことが多い証拠でもあります。ただ、聞き手にとっては情報の優先順位がわかりづらくなることも。最初に「結論」を伝えてから、理由や背景に進むよう意識すると、話がスッキリまとまりやすくなります。
論理的に考える練習はどうすればいいですか?
日常の中で、簡単な出来事を「結論→理由→具体例」で説明する習慣をつけてみるのが効果的です。たとえば日記にその日の感想を書くときも、この順序で書いてみるだけで、自然と整理する力が身につきます。
論理的思考ができない自分が嫌になるとき、どうすればいいですか?
その感情が出てくるのは、自分を良くしたいという前向きな気持ちの裏返しです。まずは「今、そう感じている自分」に気づいてあげるだけでも、心は少し落ち着きます。そして、苦手なことだけに目を向けず、自分の得意な部分にも意識を向けてみてください。視点を変えることで、自分自身との向き合い方が変わってきます。